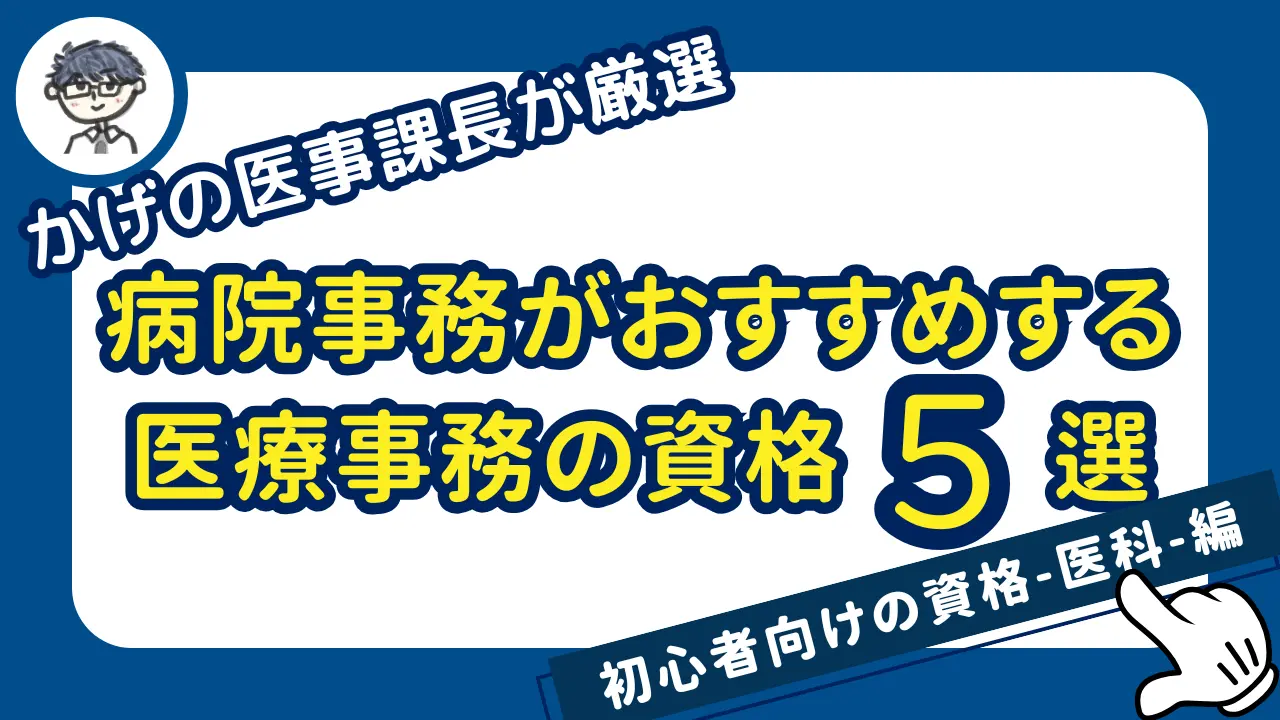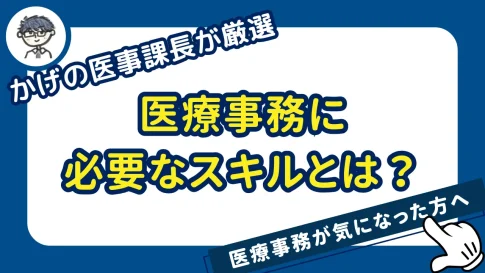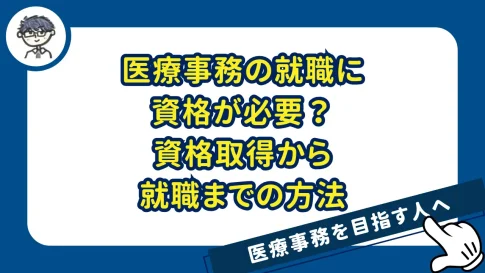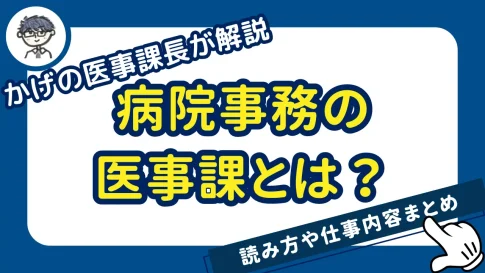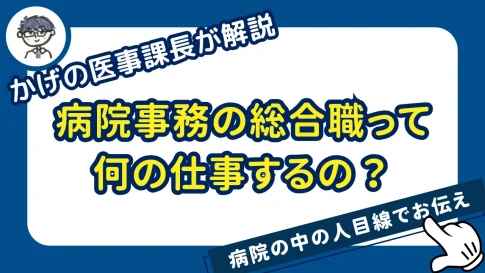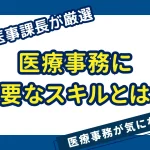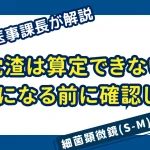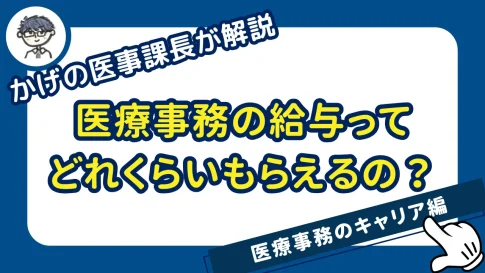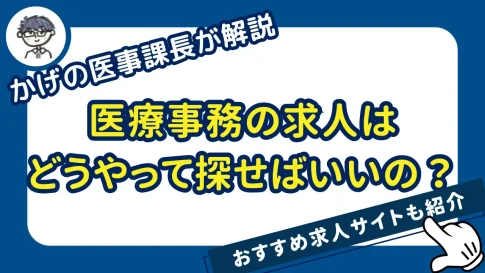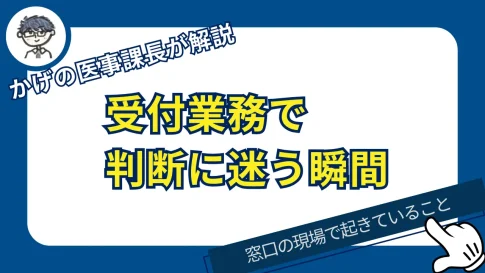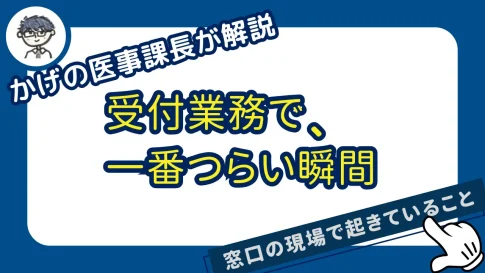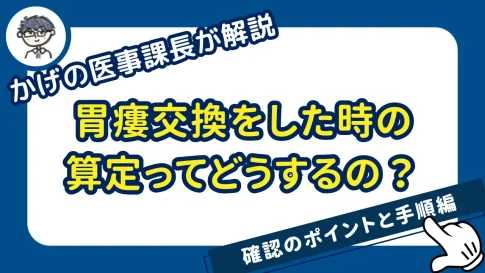医療事務としてのキャリアを考えた時、「資格取得に挑戦しよう!」と考える人は多いです。
「就職には資格が必要なのかな?」「キャリアアップのために資格とってみようかな」
そんなことを思ったことはありませんか?
医師や看護師と違って国家資格はないため、医療事務の就職活動に資格が必須となることはありません。
必須ではありませんが、取得しておくことで就職や転職が有利になったり、給与面でも評価される場合があります。
とはいえ、「資格の種類が多すぎて、どれを選べばいいか分からない…」という声も多く聞きます。
医療事務に係る資格は基本的に各種団体や企業が中心に認定している民間資格であり、その種類は多岐にわたっています。
しかし、就職時のPRや医療事務の専門知識を身につける上では、自分に合った資格に挑戦することは非常に重要となります。
本記事では、医療事務資格(医科)の種類と特徴を初心者にも分かりやすく解説します。
- 医療事務に興味がある
- 資格の種類が多すぎてどれを選べば良いか分からない
- どんな資格が自分に合っているか分からず悩んでいる

医療事務に興味があるけど、どの資格をとれば良いか悩んでる方向けの記事です。病院事務として勤務経験のある私がおススメの資格をご紹介します。ぜひ参考にしてください。
- 医療事務の資格は全て民間資格である
- 医療事務の就職については資格は必須ではない
- 4つの視点で自分にあった資格を探す
目次
医療事務資格はどんな種類がある?

まずは、医療事務の資格について、全体像をみていきましょう。
国家資格と民間資格の違い
医師や看護師などは国家資格であり、国家資格とは国の制度に基づいて認定される資格を指します。一定の知識や技術、能力等を保有することを国が証明するため、一般的に社会的な信頼度は高いとされています。
一方の民間資格は、各種団体や企業等が独自に証明するものです。国家資格ほどではありませんが、資格によっては社会的あるいは業界内においては信頼度が高いとされるものもあります。
民間資格は就職や転職、キャリアアップにつながるものから、趣味やスキルアップになるものまで幅広い内容がありますが、合格率や取得の難易度なども様々です。
医療事務の資格は後者の民間資格に該当しています。
多くの資格が存在しているため、資格取得に挑戦する際は「どれがいいんだろう…」と悩む要因の1つとなっています。
初心者におすすめの医療事務資格
医療業界が初めて!という初心者さんには、まずは自分に合った資格を探すことをおすすめします。
オンラインや在宅で受験できたり、参考書やテキストを見ながら解答したり、と受験方法も様々なものがあります。
また、受験にあたって対策講座(通学や通信教育)を受講することもできるため、独学で頑張るのはしんどい…という方も安心して資格取得に臨むことができます(なんなら、資格取得後の仕事紹介まで、トータル的にサポートをするサービスもあるようです)。
それでも「どんな資格を目指せばいいのか分からない!」という方には、医療制度を深く取り上げて出題されるものをおすすめします。
病院に勤務している私としては、やはり最低限の基礎知識として医療制度の理解は重要と思います。
クリニックや病院においても法律や規則は遵守しなければならず、それは事務の業務にも関連するものがあるからです。
とはいえ、「覚えるもの多いってこと?」「内容が難しそう…」と身構える必要はありません。
無資格・未経験で地方の病院に入職したこの私が、半年くらいで実務をこなせるようになっていたのですから、この記事をご覧になって資格取得を検討されている皆さんは、もっと早くこなせるようになることでしょう。
資格取得を通じて学んだ医療業界の基礎知識を身につける皆さんは、医療機関へ入職する時点で、私とは違って大きなアドバンテージを持つことになるんです。
皆さんなら、自信を持って医療業界への一歩を踏み出せますよ!
主な医療事務資格一覧とそれそれの特徴

初心者向けのおすすめする資格として、今回は下記の5つをご紹介します。
医療事務技能審査試験(メディカルクラーク(R))
医療事務技能審査試験(メディカルクラーク(R))は一般財団法人 日本医療教育財団が運営している認定資格です。
昭和49年度からの50年で総受験者数は171万人、合格者数は99万人を超えています。本試験を団体で受験する教育機関等(専門学校や短大、大学、職業訓練校等)も数多く登録されており、医療事務関係としては最大規模の試験となっています。
(公式サイトより抜粋)
認定試験としては古くからの実績があり、さらに試験も毎月実施しているため、受験がしやすいです。
学科と実技に分かれての試験がありますが、いずれも参考資料を見ることができるため、暗記が苦手な方でも安心です。
窓口での患者対応や診療報酬明細書(いわゆるレセプトのこと。会計業務に関係します。)作成の実務経験のある私が試験範囲を見ても、広く浅く知識を身につけたい!という方にはピッタリな試験と思います。
学科と実技いずれも医療事務として求められる範囲は全般的にカバーしている印象であり、必要な基礎知識はこの試験勉強で身につけられると思います。
医療事務技能認定試験
「医療事務技能認定試験」は技能認定振興協会が運営しており、クリニックや病院の窓口業務や会計業務を中心にカバーした資格試験で毎月実施されています。
一般的にイメージされる医療事務の業務については、この試験勉強で概ね対応ができます。
こちらも毎月試験日が設定されており(2025年度の場合)、受験はしやすくなっています。
なお、出題範囲には「実技は外来のみ」「実技・学科ともに200床未満の医療機関に限定した範囲」と記載されていることから、クリニックや小規模または中規模の病院での実務を想定した内容となっているようです。
医科 医療事務管理士®技能認定試験
「医療事務管理士®技能認定試験」も技能認定振興協会が運営しており、毎月受験が可能です。
出題範囲は前項の「医療事務技能認定試験」と同じですが、「医療事務管理士」の試験には実技に入院の診療報酬明細書作成も含まれています。
どちらかと言えば、病院勤務の方向けの内容と言えるでしょう。
こちらもクリニックや病院の窓口業務や会計業務を中心にカバーしています。
医療事務検定試験
「医療事務検定試験」は日本医療事務協会は運営している認定試験です。
こちらは実技に入院の診療報酬明細書の作成が含まれていることから、病院勤務の方向けの内容となっています。
他試験と同様、基本的な医療制度に係る内容が学科の出題範囲とされています。
その他の関連資格
全国医療福祉教育協会が運営する「電子カルテオペレーション実務能力認定試験」や「医師事務作業補助者実務能力認定試験」、技能認定振興協会が運営する「ホスピタルコンシェルジュ®検定試験」などがあります。
近年では医療業界でもIT化が進み、電子カルテの普及率も上昇してきています。また、優秀な医師事務作業補助者は多くの医療機関で確保したい人材ですし、患者応対時の言葉遣いや接遇マナーというのも、耳にすることが増えています。
上記の資格取得から少しずつ医療業界に踏み入れていく、というのもキャリアの選択肢としてはアリだなと思いますね。
興味のある内容であれば、これらの認定試験もぜひご検討してみてはいかがでしょうか?
資格選びのポイント

前述のとおり、たくさんある医療事務の資格ですが、何を基準として選んでいけばよいのでしょうか。
自分に合った資格を選ぶポイントをお伝えします。

たくさんあると、何がいいんだろう?と迷っちゃいますよね!
やりたい仕事の内容で選ぶ
医療事務といっても様々な仕事があるため、具体的に「こんな仕事をやりたい!」とイメージがある方は、実務に直結する資格を優先的に選ぶこともおススメです。
仕事内容に応じて求められる知識やスキルは異なりますよね。
クリニックや病院の顔とも言える「受付」では、医療制度の知識や接遇といったコミュニケーションスキルが求められますし、医師専属のサポートである「医師事務作業補助」では医療用語の知識の他、PCのタイピングスキルが求められます。
どのような仕事をやりたいかを先に考えてから資格を選ぶと、将来の仕事の具体的なイメージをつかみやすくなります。
就職のしやすさで選ぶ
具体的に気になる就職先があるのであれば、求人票を参考にしながら資格を選ぶこともできます。つまり、就職へのつながりやすさの視点で選ぶことです。
医療事務の就職にあたっては資格は不要ですが、医療業界の基礎知識を持っているかどうかは就職の際にPRになり得ます。
いくつかの求人票を眺めてみると、「〇〇の資格をお持ちの方、優遇します!」といった記載を見かけることがありますので、医療事務としての就職を検討している方は募集要項も注意深く確認してみてください。
自分が気になる求人票に具体的な資格の名称があった場合、実務に直結する可能性が高い資格です。
学習期間・難易度で選ぶ
どうせやるからには、絶対合格したい!と思うのは誰もが同じです。
しかし、同時に「自分には難しすぎないかな…」と不安に感じることもあるでしょう。
そんな時には試験の学習期間や難易度で選ぶことも選択肢の1つです。
「医療に関連する勉強は初めてだから、まずは初心者向けの資格から始めたい!」といった場合では、合格にあたってどの程度の勉強が必要なのか、また、その試験の合格率はどれくらいか、といった情報は貴重です。
自分にも合格できそうなイメージが持てるか、学習時間は確保できそうか、といった視点で資格を選ぶこともよいでしょう。
受験費用で選ぶ
受験もタダではありません。
費用がいくらかかるのか、といったコストの視点で資格を選ぶこともアリです。
ざっくりとした費用の相場感でいえば、5,000円くらいは見積もった方がよいです。
中には10,000円を超える資格もあれば、3,000円程度で受けられるものもありますが、実際には受験費用の他、テキストの料金、試験会場までの交通費等も加味する必要があります。
まずは手の届く範囲で受験してみようかな!といった選び方にはおススメです。
まとめ:目的に合った資格を選ぼう

ここまで解説してきましたが、自分に合いそうな資格は見つけられましたか?
私自身、文系の大学を卒業後に病院事務として医療業界に飛び込みましたが、就職にあたっては資格取得そのものは不要と考えています。
実務を行う上では必要最低限の知識は身につきますし、資格がないから困る!といったことはありません。
それでも、資格は医療事務としてのキャリアを考える上では、自分のスキルアップや実力試しとしては大いに活用したいと思えるものだと考えます。
医療事務に興味を持っている皆さんには、ぜひ医療業界への一歩を踏み出していただき、一緒に頑張っていきたいなと思います。
一緒に頑張っていただける方、資格取得のサポートが欲しい方はコチラものぞいてみてください!