
「医療事務って具体的にどんな仕事をするの?」という疑問を持つ方は多いでしょう。
受付や会計のイメージが強いかもしれませんが、医療事務の仕事はそれだけではありません。
レセプト作成や診療報酬請求、患者さんの対応や行政機関との応対など多岐にわたります。
この記事では、医療事務の仕事内容と必要なスキルをわかりやすく解説し、これから医療事務を目指す人が業務の全体像をつかめるようにします。
目次
医療事務とは?

一般的なイメージでは医療機関に勤務する事務職員を指しますが、本記事ではクリニックや病院で患者応対や保険請求を担当する事務職員として解説してきます。
とはいえ、薬局の調剤事務も「医療事務」ですし、医師事務作業補助者も「医療事務」ですので、広義の意味では、「医療事務」は幅広い範囲を指す点はご留意ください。
クリニック・病院での役割
「どうせ、事務なんて地位が低いんでしょ?」
そう思う方は、古い考えをもお持ちの方です。
クリニックや病院における医療事務は、医療機関の顔でありながらも、経営の中枢を担う非常に重要な役割を担います。
患者応対から会計など様々な業務を担当しますが、それらは医療機関の経営に非常に重要な役割を持っているからです。
あなたが医療機関に受診しに行った時のことを想像してみてください。
対応してくれた事務員さんの言葉遣いが変に馴れ馴れしかったら?
案内の通りに院内を移動したら、いろいろとたらい回しにされてしまったら?
ようやく帰れると思ったのに会計金額が誤りだと後からわかったら?
あなたは医療機関に対して不信感を抱き、もう絶対行きたくない!と思うでしょう。
そして、その出来事を家族や友人に話し、その医療機関に対する周囲の人の印象も変わっていきます。
医療機関を訪れた時、最初に出会うのは医師の先生ではありません。
受付の事務です。
そして、診察が終わって帰る時も、次回の予約や会計の案内をされるのも事務です。
そう、患者さんが最初と最後に接する職員が事務なのです。
どんなに丁寧な診察で「先生に診てもらってよかった!」と感じても、最後の案内が雑で悪い印象であれば、その医療機関からは患者さんは離れていきます。
私の先輩は「優秀な事務がいる医療機関は、必ず経営が上手くいっている」という言葉を何度も言い聞かせてくれました。
私が病院事務として経験を積めば積むほど、これは間違ってないと感じる言葉です。
「患者が来たら受付して会計して一日が終わる簡単な仕事でしょ?」と思ってる方には、医療事務の仕事はおすすめしません。
縁があって医療機関に採用されたとしても、入職前後のギャップについていけず、いずれ退職につながるからです。
それだけ医療事務の仕事は、医療機関において重要な役割を担っているのです。
医療事務と受付・クラークとの違い
病棟にいる事務(クラーク)も、受付にいる事務も、広い意味では同じ「医療事務」です。
「医療事務」は広義の名称であり、実際には担当する業務に応じて「クラーク」「医師事務作業補助者」等と細分化された呼称で呼ばれることが主流になっています。
「医療事務」は診療報酬や医療制度に係る知識が求められる事務であることから、総務や経理など一般的な管理系の事務とは区別されます。
【医療事務のイメージ図】

医療事務の主な仕事内容

医療事務は患者さんに係る多くの業務を担当します。
具体的な業務内容について、みていきましょう。
受付業務(患者対応)
基本的な業務であり、患者さんからも見えるのでイメージしやすいのではないでしょうか。
運用の違いはあっても、クリニックも病院も基本的には同じ業務内容です。
受付業務の流れ(例)
- 患者の保険証情報を確認し、初診か再診か、何かを受診するのか等を確認する
- 診察券の発行や問診表の記載依頼、カルテの作成を行う
- 医師や看護師に申し送りを行う
その他、診断書などの書類申請に対応したり、院内外からの電話応対なども業務に含まれます。
会計業務(窓口精算)
診察や処置等が終わったら、後は会計ですよね。
この部分も患者としての受診経験がある人はイメージしやすいと思います。
会計業務の流れ(例)
- 医師や看護師などから申し送りを受ける
- カルテや指示書を確認しながら、データをPC(レセプトコンピュータ)へ入力する
- 請求書を発行する
- 患者さんに支払いをお願いする
- 金銭の授受をする
- 処方箋や次回予約などの案内をする
会計データの入力中に疑義があった場合、医師や看護師に内容を確認したり、医科点数表(計算のルールブックのようなもの)で調べることもあります。
診療報酬請求業務(レセプト作成)
一般の方には馴染みのない用語ですが、レセプト(診療報酬明細書)作成も医療事務の主な仕事の1つです。
医療制度に関連するので本記事での詳細な解説は省略しますが、医療機関の収入の大部分を占めるレセプト(医療費の請求書のようなもの)を作成します。
レセプトは患者さんに渡す請求書・明細書と同様の内容となりますが、毎月10日前後の提出期日に間に合うよう、月末から月初の短期間で集中的に提出準備を行います。
診療報酬請求業務の流れ(例)
- カルテや指示書を確認しながら、データをPC(レセプトコンピュータ)に入力する
- レセプト作成のルールに則り、医療費の請求過剰、請求漏れがないかチェックする
- 診療行為に対して適切に医師の診断病名の入力がされているか確認する
- 必要に応じて医師と相談し、臨床的な所見や診断病名の入力を依頼する
- レセプト作成のルールに則り、必要なコメントなどを記載する
- レセプトの提出用データを作成する
- レセプトデータを提出する
提出するレセプトデータは審査支払機関や保険者というところで審査され、審査結果に応じて医療機関に診療費の一部が支払われるため、レセプトの作成は適正・適切な内容であることが求められます。
その他の事務業務(書類管理など)
患者さんから依頼された診断書作成の進捗管理や完成後の引き取り連絡、また、行政機関への書類回答といった業務もあります。
それ以外にも物品や備品の補充・発注、会議資料の作成や他部署との連絡調整といったものもあります。
医療事務に必要なスキル・知識

主な仕事の内容は前述の通りですが、ここからは仕事に必要なスキルや知識をみていきましょう。
医療保険制度の知識
患者さんへの案内はもちろん、会計やレセプト作成業務には必ず医療保険制度の知識が関係してきます。
したがって、制度に関する知識は実務においては非常に重要な意味を持つのです。
また、医療保険制度の内容は定期的に見直しが行われます。
したがって、最新の業界情報を収集していく必要がありますし、院内運用を変更して制度の変更に対応していくことが求められます。
パソコンスキル
多くの医療機関では電子カルテの導入が進んでおり、業務のほとんどでPCを使います。
特別なPCスキルは不要ですが、ある程度タイピングやマウスの操作に慣れておく必要があります。
ブラインドタッチができる、というようなレベルは不要ですが(私もできない)、ローマ字入力ができる程度はなっておきたいところです。
また、可能であればMicrosoft officeのWordやExcelの操作感は慣れておくと良いです。
太字にする、文字の色を変更する、グラフの挿入をする、といった基本的な操作ができると実務では重宝します。
コミュニケーション能力
コミュニケーション能力は特別なスキルではありませんが、どんな仕事でも必要です。
それは医療事務においても例外ではありません。
事務同士はもちろん、医師や看護師など多職種と連携を取りながら仕事を進めるため、コミュニケーション能力が求められる機会は日常的に多いです。
相手が多忙な時は端的に情報を伝える、難しい内容は例え話をとあわせて共有する、といった状況に応じたコミュニケーションの取り方が重要となります。
また、医療事務が応対する相手は患者さんです。
病気を持っている方であり、お客さんではありません。
案内時の言葉遣いや相手の言いたいことを汲み取るといったスキルは、非常に重宝されます。
医療事務のやりがいと大変さ

一般的には簡単な仕事と思われがちですが、実は窓口業務以外にも重要な仕事をこなしている医療事務であることはお分かりいただけたのでしょうか。
そもそも医療は社会的な貢献度が高い分野のため、やりがいを感じる機会は多いです。
例えば窓口に立っていると、会計が終わった患者さんやその家族から「ありがとうございました」「お世話になりました」と言われることがあります。
感謝の言葉とともに患者さんが笑顔で帰っていく姿を見ると、「無事に病気が治って良かったな」「自分の仕事(職場)はこんなにも人から喜んでもらえるものなんだ」と嬉しくなります(自分が直接治療したわけではありませんが)。
もちろん、仕事をする上では大変なこともあります。
レセプトの業務には毎月10日前後の提出締め切り日があるため、毎月業務のピークを迎えることになりますし、感情的になった患者さんから理不尽な言葉を投げかけられることもないわけではありません。
それでも私が医療事務としてのキャリアを続けているのは、今の仕事を楽しめているからだと思います。
経験年数を経て、窓口での案内からは離れる機会が多くなり、クレーム対応や会議資料、経営企画提案などの仕事も増えています。
患者さんから直接感謝の言葉を聞く機会は減っても、病院の経営をうまく回して地域社会への貢献をしている自覚はありますし、一緒に仕事をしている医師や看護師、事務部の他課から感謝の言葉を聞く機会はあります。
大変だからこそやりがいを感じる、という部分もあるのかな、と思っています。
まとめ:仕事内容を理解してから資格や求人を検討しよう

せっかく勉強を頑張るのであれば、取得した資格は無駄にはしたくないですよね。
資格を無駄にしないためにも、まずは医療事務の仕事内容を理解することをおススメします。
「どんな仕事があるのかな?」「こんな仕事をやりたいかも」と考えることは、医療事務の理解を深めることにもつながります。
そして、仕事内容が分かると、「どんな資格が自分に合うかな?」「窓口がメインの仕事だとビジネスマナーの資格が役立ちそう!」と、具体的なイメージを膨らませることができます。
せっかく医療機関に入職するからには、やはり長く医療事務を続けていきたいですよね。
「こんな仕事をするとは思わなかった!」と入職前後のギャップを感じると、仕事は長続きしなくなってしまいます。
そうならないためにも、「医療事務ってどんな仕事をするんだろう?」「どんな知識・スキルを身につけると仕事で活躍できそうかな?」と興味を持ち、入職前にいろいろと情報を集めていきましょう!
「医療事務目指したいけど何から始めれば良い?」といったお悩みの方は連絡ください!
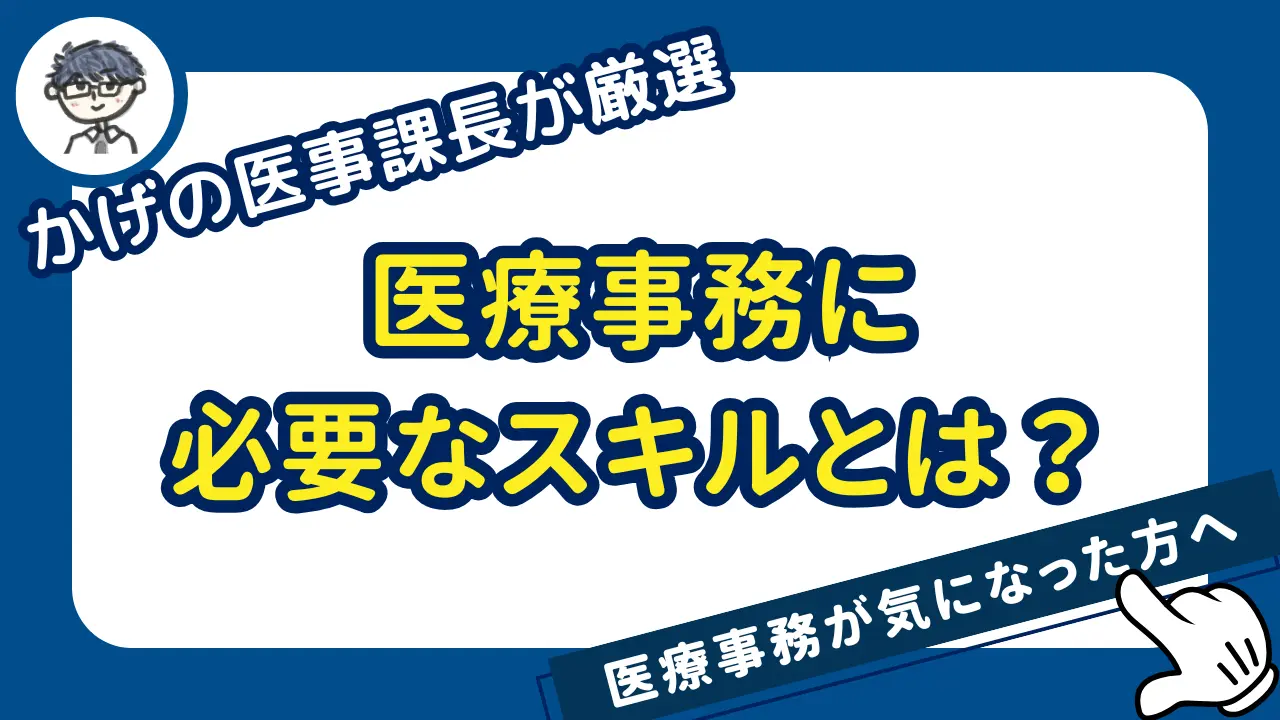
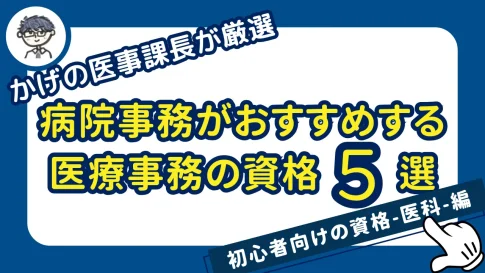
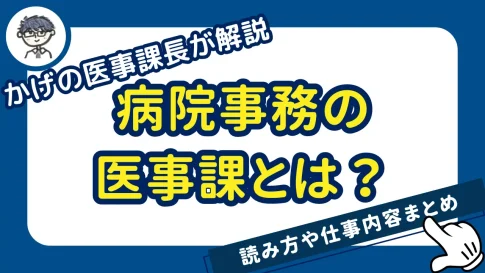
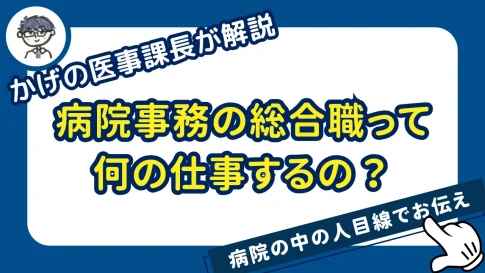
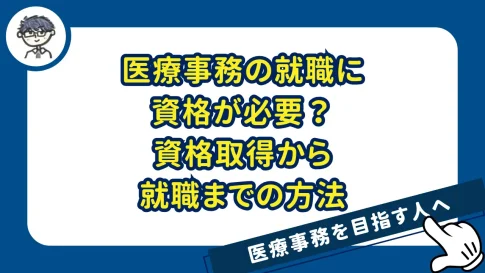
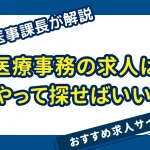
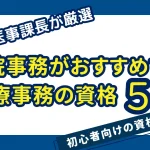
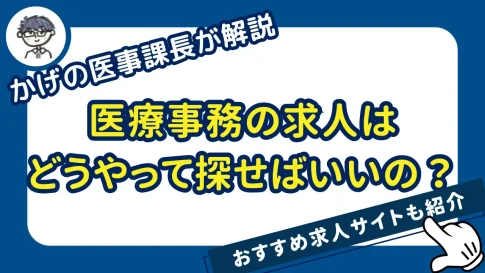
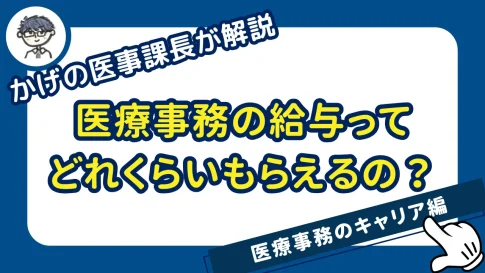
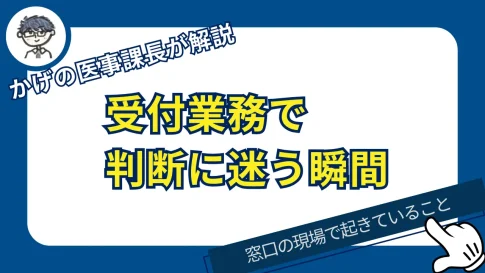
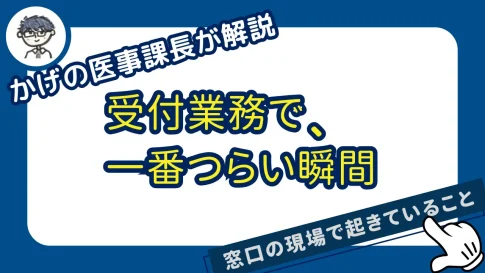
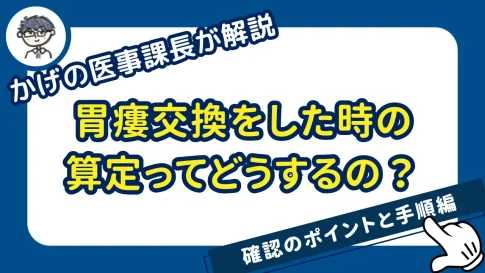
病院事務としての仕事に興味がある方に説明するイメージでまとめていきます