
「病院の事務ってどうなの?」と質問を受ける機会が最近増えてきたので、中~大規模クラスの総合病院の経験をもとに、お仕事の内容などについてご紹介しようと思います。
この記事をおススメする方は下記を対象としています。
- 医療業界への就職に不安を感じている人
- クリニックの事務から病院の事務へと転職を考えている人
- 病院の総合職ってどうなんだろう?と興味がある人
管理人の情報についてはコチラをご覧ください。
目次
病院事務総合職の仕事内容とは?一般的な事務職との違い

病院事務総合職は、一般的なオフィスワークとは異なる点が多く、医療現場の一員として重要な役割を担っています。
病院という特別な環境でどのような業務が求められ、他の事務職と何が違うのかを知ることで、業務内容の理解が深まります。
まずは病院事務総合職の具体的な仕事内容について解説します。
病院事務総合職の主な業務内容
病院事務総合職は、病院の運営をサポートするための多岐にわたる業務を担当します。
患者さんの情報管理、医療機器や薬品の管理、職員の給与計算など、業務の範囲は広範囲にわたります。
病院も組織なので、もちろん総務や経理、人事といった部署はもちろん存在します。規模によっては、「総務・経理課」のように複数の部署を統括する病院もある一方、管理部門はまとめて法人部門がまとめて管理をする病院もあります。
一般的な事務職との違い
病院と一般企業の事務職を比較して大きく違う点は、患者さんの応対やカルテ管理、診療報酬の請求業務があることです。
これらの業務は医療知識や専門的なルールに従って業務を行う必要があるため、例えば、患者情報の取り扱いや医療保険制度に関する専門知識が求められます。
そのため、病院事務には法律や診療報酬に関する知識は必須となり、日々の業務でも専門的な判断を迫られることが多くなります。
電子カルテやレセプトコンピュータを使用しながら業務を進めていくため、一定程度システムのサポートがありますが、まだまだ人間のスキルレベルに頼る部分が大きいです。
多くの病院では「医事課」という部署が患者応対や診療報酬の請求業務を担いますが、病院によっては業務委託をする場合もあります。
実際、私の勤務病院では、外来(入院ではない、通院する方)部門の窓口は民間企業に委託をしています。
知り合いの病院に話を聞くと、すべて正職員(総合職)のパターンや、窓口は委託で会計業務は正職員といったパターンもあるようです。
医事課業務のイメージがつかめない方のために、職業紹介として厚労省が作成した動画をご紹介します(Youtubeに遷移します)。公開時期が2020年なので少し情報が古いですが、参考になると思います。
病院事務総合職に求められる能力
前述のとおり、病院事務総合職には、一般的な事務スキルに加えて、医療業界特有の知識や対応力も求められます。
一般的に病院の事務と言えば受付や会計業務のイメージを持たれますが、実際にはそれだけではありません。
患者さんのカルテ管理、病院内の資産管理や経営企画など、医療現場を円滑に運営するために不可欠な役割を果たします。
医療業界で働く不安を解消するための最初のステップ

初めて医療業界での仕事を目指す際に、不安を感じるのは当然ですよね。
特に病院の事務の場合、「一般的な事務職なにが違うんだろう?」「病院の環境って特殊そう…」と戸惑うこともあると思います。
しかし、事前にしっかりと準備をすることで、不安を解消して自信を持って入職することができます。
このセクションでは、医療業界で働く不安を解消するための第一歩として、どのような準備が必要なのかを紹介します。
医療業界の基本的な知識を身につける
業界知識は少しで良いから知っておこう、ということですね。
まったく知らないよりも「なるほど、こうなっているのね!」と少しでも自分の理解が及ぶものになれば、不安を軽減できます。
医療業界には専門的な用語やルールが多いことは事実です(が、これは他の業界でも同じことが言えます)。
入職後に研修があるとしても「そもそも病院ってどういう組織なんだろう?」「業界的に今後の見通しはどうなっていくのかな?」といった全体像は理解しておきましょう。
ですが、詳細に理解する必要は全くないのでご安心ください。

配属される部署ごとに求められる知識も変わってくるので、入職前では「医療業界について、なんとなく分かった!」くらいのレベル感で問題ないです。
予習する内容としては医療保険の仕組みや診療報酬制度、病院とクリニックの違い等に関する基本的なところをおさえておくだけで十分です。
医療業界特有の文化やマナーを学ぶ
医療業界で働くためには、業界特有の文化やマナーを理解することが重要です。
「特有の」とは言ったものの、あまり身構える必要はありません。
例えば、対応するのが患者さんであれば、接遇として言葉遣いや気遣いをとくに注意しましょうね、院内職員であれば、なるべく簡潔に内容を伝えましょうね、というくらいです。

一般企業と異なる特徴の1つとして、「応対するのは【患者】であること」が挙げられます。何かしらの病気や症状で悩んで来院される点は念頭に置く必要があります。
病院事務は患者さんや医師、看護師等多くの人とコミュニケーションをとりながら仕事を進めていきます。入職時点では一般的な敬語や作法ができれば問題ないです。
「就活でのPRポイントにしたい!」とか「自分に自信を持って臨みたい!」という方は資格試験に挑戦するのもアリです。
自信を持って業務に取り組むために
入職後に自信を持って業務を行うためには、まず小さな成功体験を積むことが大切です。
初めての仕事や環境に不安を感じるのは当然ですが、小さな仕事を着実にこなすことで、自分自身に自信を持つことができ、不安が解消されていきます。
最初は簡単な業務から始め、徐々に難易度の高い業務に挑戦することで、徐々に自信をつけていくことができます。

中途採用で前職が同じ病院事務だとしても、やっぱり入職当初は不安に感じるものです。焦らず、毎日の成長を楽しむくらいの気持ちで臨みましょう。
また、充実した研修体制のある職場を選んだり、同僚や上司からのサポートを得られることも心強く感じられます。
病院事務総合職で求められる基本スキル

病院事務総合職に就くために「特別なスキルが必要だろうか?」と不安に思っている方も多いかもしれません。しかし、実際には専門的なスキルや資格がなくても、基本的な事務職のスキルさえあれば十分にスタートできます。このセクションでは、病院事務総合職で求められる基本スキルについて、具体的に解説します。
一般的な事務スキルが基本
病院事務総合職には、一般的な事務職で求められるスキルが基盤となります。
電話対応や書類作成、データ入力など、オフィスでの一般的な事務作業がメインの業務となるため、基本的な事務スキルが必須です。
極論かもしれませんが、最低限としてPCのキーボード入力ができれば問題ないです。
電子カルテや経理管理ソフトなど使用するシステムや院内運用については、入職してから徐々に覚えればOK。病院によって採用しているものが異なるので、この点はあまり心配しなくて大丈夫です。
電話応対を基本として、PC操作(Word、Excelなど)やメールでの連絡調整などの事務職にも共通するスキルは、病院事務でも同様に重要です。
医療業界特有の知識を学ぶ
医療や診療報酬の知識が求められる医事課においては、診療報酬明細書(以下、レセプト)の作成スキルが重要です。
「病院の顔としてやっぱり医事課配属になりたい!」「病院に入職するからには医事課で頑張ってみたい!」入職前に夢や目標が決まっている方は、入職前から基礎知識を学ぶことは大切です。
医療現場には独自の規定やルールがありますが、基本的な医療用語や医療制度を理解しておくことでスムーズに業務をこなせます。
例えば、診療報酬の仕組みや保険請求に関する知識は、最初に学んでおくべき基礎知識であり、業務で頻繁に使う場面が多いためです。

私自身は、無資格・未経験で病院事務に入職しました。医事課に配属された経験を振り返ると、「資格は必須ではないけれど、基礎知識があると理解が早くなれただろうな」と思います。
やる気がある方に向けてお伝えすると、勉強の方法はいくつかありますが、医療業界の経験有無によって変えるのが良いかなと思います。
例えば、「医療業界に入るのは初めて!」という方であれば、入門的な参考書一冊を軽く一読する程度であまり費用はかけなくても良いかなと思います。
ステップアップとして病院への入職を目指す方は、レセプトの作成の基礎あたりは理解した方が良いかと思います。
コミュニケーション能力が鍵
病院事務総合職には、患者さんや医療スタッフとの円滑なコミュニケーションが求められます。
医療現場では、患者さんの対応や医師との連携が必要不可欠です。

事務も積極的に関わり、病院の運営・経営に貢献していくことが求められます。
自分の考えを的確に伝え、相手の意図を正確に理解する能力が重要です。
患者さんや医師に説明する場合、時には自分の考えを支持するような根拠の提示が必要になり、ロジカルな話し方を求められることもあります。
近年の就活では「コミュニケーション力が重要視される」といった声を聞きますが、病院事務職においてはその傾向はより強くなります。
患者さんへの対応やスタッフとの協力がスムーズに行えることで、業務の効率が大幅にアップし、院内外で信頼を得やすくなります。
就職活動を進めるための不安解消アドバイス

いざ「病院事務になりたい!」と思っても、不安に思うことは多々あると思います。
不安解消の方法として、いくつかご紹介します。
不安に思うことを書き出してみる
漠然とした不安が何によるものかを書き出してみることもおススメです。
不安の多くは「知らないこと」に起因します。知識を深めることで自分の中で理解が進み、安心感が得られます。
就活の進め方、求人情報を見るときのポイント、医療業界の知識や業務に関する情報など不安になり得るものはいくつかありますが、まずは不安の原因を特定することからはじめます。
原因の特定ができたら、どのように解決するかを考えていきます。
私の経験では、何もしないことが不安や焦りを感じる場合があるので、まずは行動に移してみることが重要だったりもします。
不安を感じたら、周囲に相談してみる
不安を感じたときは、友達や家族に相談することが大切です。
1人で抱え込むとさらに不安が増すことがあります。周囲のサポートを受けることで、問題が早期に解決しやすくなります。
知り合いに医療従事者がいない方でも、私にできることであれば喜んで相談に乗ります!
お気軽にご連絡くださいませ。
小さな成功体験を積み重ねる
不安を解消するには、小さな成功体験を積み重ねることが効果的です。
就職活動を進めていく過程ではやるべきことをリスト化し、小さな作業に細分化して書き出すと進めやすくなります。
例えば、就活の中では履歴書の提出が求められますが、その作業を分解していくと、「証明写真を撮る」、「志望動機を書く」、「自己PRを書く」というように細分化できます。
さらに詳細にすると、どこで証明写真を撮るか(カメラ屋さんまたは撮影機)とか、自己分析をする(自分の得意なこと、不得意なこと、好きなこと等々を文章化する)といったようになります。
細分化すると終わった後はリストにチェックをつけられるので、全体の進捗状況や自分が実行できた量を実感することもできます。
小さな成功体験を積むことで、自己効力感が高まり、不安を感じにくくなります。
達成感を感じることが、モチベーションアップにつながります。
病院事務総合職でのキャリアアップとやりがい

病院事務総合職で働き始めると、最初はさまざまな不安や挑戦があるかもしれません。
しかし、それらの不安を乗り越えることで、医療業界でのキャリアが大きく広がります。このセクションでは、病院事務総合職としてのキャリアを成功させるために、どのような心構えで取り組むべきかを解説します。
長期的な視野を持つ
病院事務総合職でのキャリアを築くには、短期的な不安を乗り越えて、長期的な視野を持つことが重要です。
診療報酬制度が2年に一度のペースで見直されることもあり、医療業界は変化が多いです。制度の見直しに合わせて病院の経営方針や院内運用も変更する場合がありますが、短期的な不安に焦るのではなく、着実に経験を積みながら長期的な成長を目指すべきです。
医療事務の役割は、患者さんの対応だけでなく、医療経営や事務作業全般に関わるため、時間をかけて専門性を高めることで、昇進やキャリアアップの道も開けます。
事務の総合職という点では、適正配置や総合的な能力開発という視点から3年~5年単位で部署異動をする病院もあります。
その意味では病院特有の知識・スキルだけでなく、一般的なスキルも身につけることができます。
チームワークと協力を大切にする
医療現場で成功するためには、チームワークと協力を大切にすることが不可欠です。
病院では医師、看護師、その他の医療スタッフと連携を取ることが多いため、協力し合う姿勢が求められます。
病院事務は、単独で完結する仕事が少なく、チームで協力し合いながら業務を進めることが一般的です。円滑なコミュニケーションを築くことで、業務の効率が上がり、ストレスも減ります。

いわゆる「チーム医療」というやつです。医療の各専門職との接点という点では医事課が一番多いです。お互いに信頼できる関係構築がポイントになります。
柔軟な姿勢で学び続ける
医療業界で成功するためには、柔軟な姿勢で常に学び続けることが重要です。
医療業界は日々進化しているため、新しい技術や制度を学ぶ姿勢が欠かせません。
新たな知識を吸収するためには勉強や研修に参加することをおススメしますが、可能であれば病院の経費で参加できると良いですよね。
院内勉強会の頻度や資格取得補助制度の有無なども入職前に確認しておくとよいでしょう。
知識を常に更新し続けることで、変化に柔軟に対応できるようになります。
FAQ
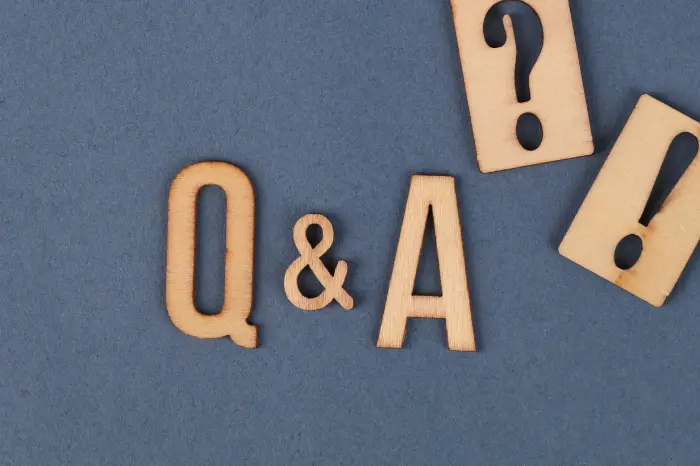
よくある質問とその回答について、下記に掲載します。
まとめ

病院事務の総合職は、医療現場での事務全般を担当し、特別な資格はなく、基本的な事務スキルがあれば就職可能です。無資格・未経験でも入職できることは私の経験が証明します。
医療業界の知識がなくても、入職後に研修で学びながら経験を積むことができるので、その点は安心です。医事課の配属にならなければ、医療制度とはほぼ無縁と言っても過言ではありませんし、実際、人事課や総務課の方で医療制度や診療報酬に関する知識が皆無の方はいらっしゃいます(とはいえ、もちろん人事や総務の領域の知識は求められますが)。

将来的に長く病院事務に身を置くつもりがあるのであれば、医事課での業務経験は強くおススメします。病院経営の仕組みや基本を身につけることができます。
また、仕事はチームで協力しながら進め、長期的な視野を持ってキャリアを築くことが重要です。不安があっても、柔軟な姿勢で学び続けることで、医療業界でのキャリアを開花させることができます。大変な部分ももちろんありますが、その分やりがいはある仕事です。
自分に合ったペースで成長しながら、安定した給与や福利厚生を享受できる職場で働ける点も魅力の1つです。
以上、
病院事務の総合職について紹介しました。
よければコメントやSNSのフォローをお願いします!
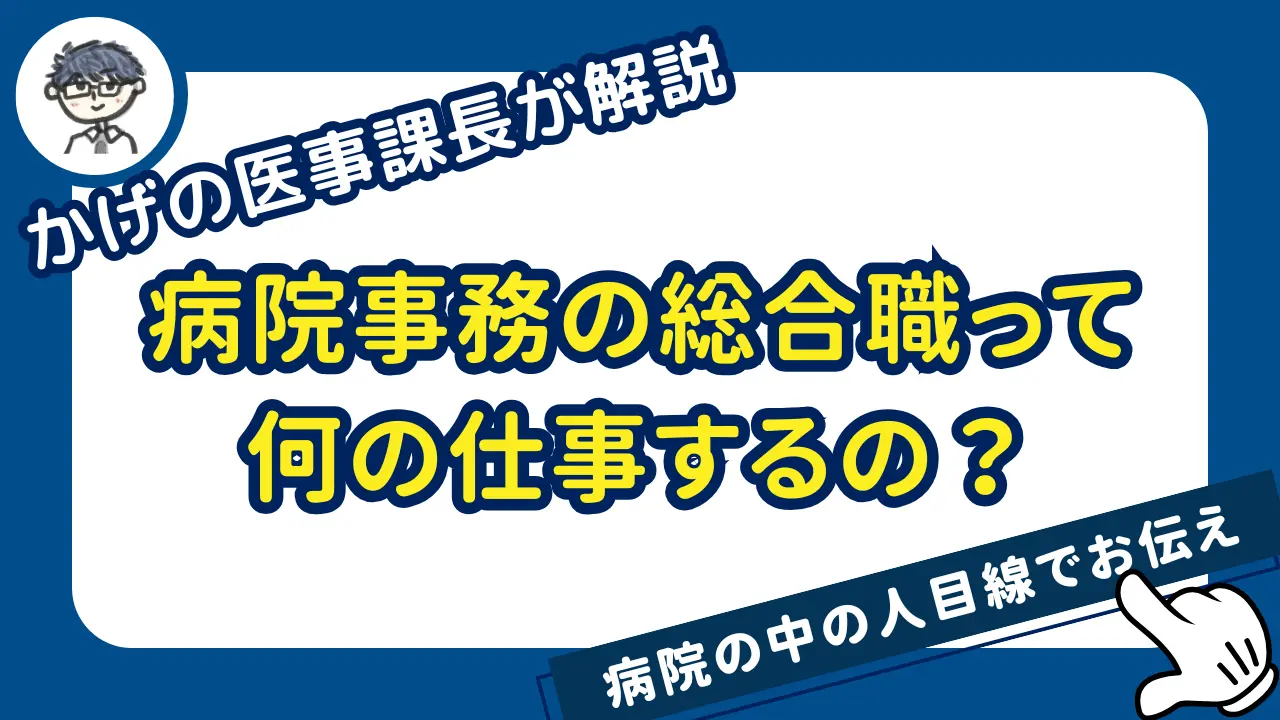
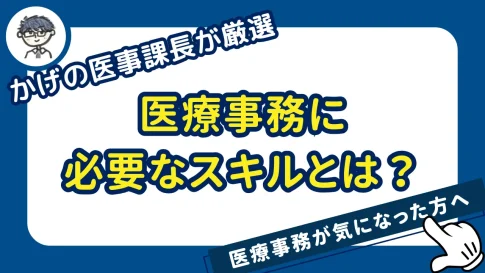
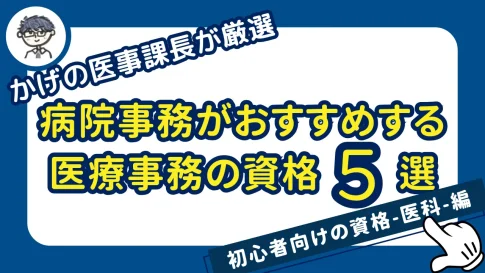
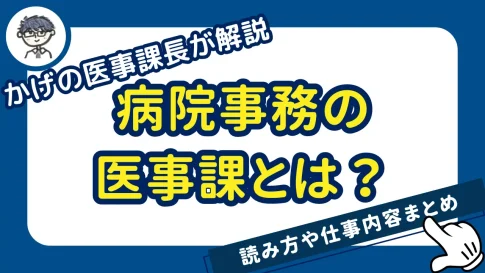
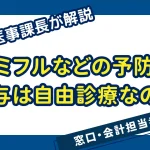
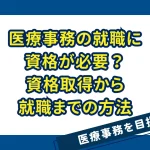
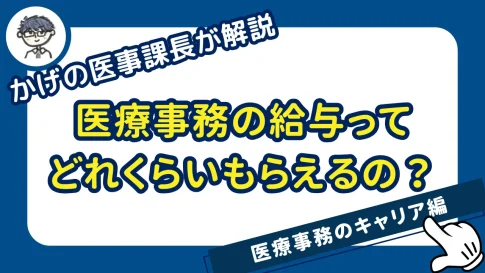
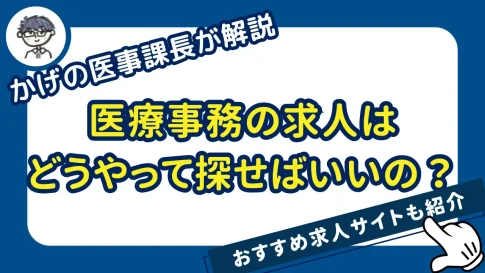
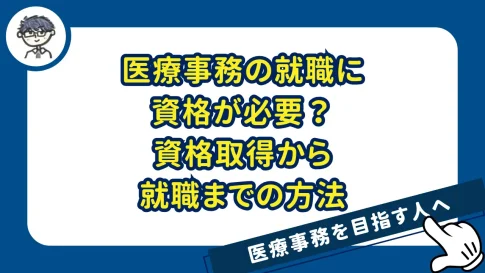
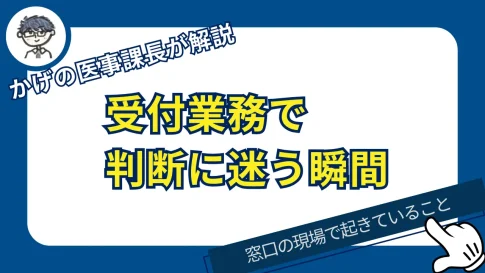
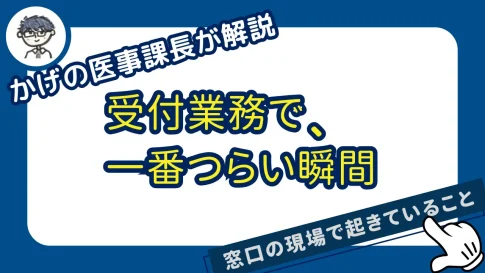
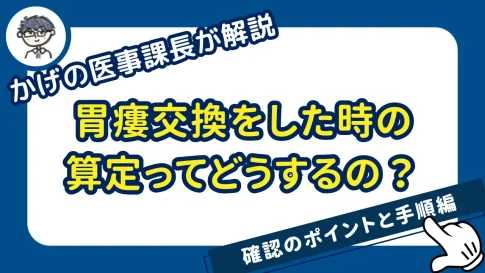
患者さんと接する仕事に就きたい!という方は、募集職種の業務内容に患者対応が含まれているかを確認してから応募しましょう。