
急性期から慢性期まで、多くの医療機関において酸素投与が行われる患者さんがいます。入院や外来、在宅問わず実施される医療行為であり、診療報酬上は「J024 酸素吸入」として1日あたり65点の点数が設定されています(2024年度改定)。
しかし、レセプト請求を担当している皆さんの中には「J024 酸素吸入」が査定または返戻となった経験がある方がいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では「J024 酸素吸入」を適切に算定できるよう、算定できないケースを取り上げながら、査定・返戻対策を一緒にみていきましょう。
※本記事は2024年度診療報酬改定制度の内容となっています。
- 「J024 酸素吸入」が算定できない理由が分かる
- 「J024 酸素吸入」を算定するためのポイントが分かる
- 酸素投与量の算定できる上限が分かる
- 「J024 酸素吸入」が適切に算定できるようになる
記事の執筆者はこんな人です。

ふと気を抜いたときにレセプトチェックが漏れてしまい、よく査定をされてしまうんですよね。自分への注意喚起の意味もあり、整理してまとめてみました。
こちらの記事もおススメです。
目次
なぜ酸素吸入が算定できないのか?算定不可の主な理由とは

酸素吸入は医療現場で頻繁に使われる処置ですが、レセプト請求の際に「算定できない」「査定された」という声が多く聞かれます。なぜ酸素吸入が算定ができないのか、その理由を理解することは、適切な請求と業務効率化の第一歩です。この記事では、算定できない主な理由をわかりやすく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
※本記事は酸素吸入に係る医学的な処置の必要性があることを前提として解説していきます。
酸素吸入の算定は診療報酬上のルールに基づいている
酸素吸入の算定には、診療報酬上で細かい要件が定められており、それを満たさなければ算定できません。医学的に必要なケースに限定して算定が認められていることに加え、類似の診療行為については主たるもののみ点数の算定ができるとされており、重複した評価(点数請求)による過剰な医療費にならない制度設計になっているためです。また、一部の医学管理料や入院料では、診療行為を含めた点数設定として、酸素吸入が包括される(算定ができない)ものとされています。
実際の医療現場では、酸素吸入の適応疾患や処置の方法、使用時間など具体的な要件があるようですが、ここでは診療報酬に係る内容についてみていきます。
算定不可のケースが増える背景は審査の厳格化にある
近年、レセプトの電子化が進み、レセプト審査も機械によるチェックが可能になりました。これまでは人為的なミスによって審査が通っていたものも、コンピューターチェックによってレセプト審査が厳しくなり、査定件数も増加しています。
(画像)
医療費抑制の動きや不適切な請求への対応が強化されているため、算定要件を満たさない請求は返戻や査定の対象となります。
厚生労働省の指導や審査支払機関のチェック体制強化により、適切な診療報酬の請求が行われるよう働きかけが行われています。
所見や検査値記録の不備、病名入力漏れにも気をつける
医師の診断に基づいて酸素吸入をした場合でも、診療録やレセプトへの記載不足で算定が認められない場合があります。
算定の根拠となる診療録への記載は必須であり、適時調査などの時に治療の必要性の証明ができないと、算定は認められません。
また、レセプトの審査では、診断病名に基づき診療内容の妥当性について審査がされ、不備や疑義があれば査定・返戻されることになっています。
酸素吸入が査定されるパターン

酸素吸入が算定できずに査定されるケースには、共通する典型的なパターンがあります。これらのパターンを理解しておけば、どんなミスが起きやすいのかがわかり、実務でのミスを防げます。ここでは、査定されやすい代表的なケースを解説していきます。
医学的必要性が認められない場合
レセプト審査上、酸素吸入の医学的な必要性があると判断されない場合は査定されます。
診療報酬のルール上、酸素吸入は患者の状態や疾患に応じて必要と判断されなければ算定できません。例えば、急性期の呼吸器疾患の疾患名の記載がない、あるいは患者の酸素飽和度の測定をしていないといった場合、審査側は「必要ない」と判断し査定されることがあり得ます。
実際の査定の事例では、軽症の患者に対して酸素吸入を算定したケースであったり、ほぼすべての症例に対して酸素吸入を算定しているケースがあります。
診療報酬上の算定条件を満たしていない場合
算定要件を満たさない場合に酸素吸入を請求すると査定されます。
例えば「J026 間歇的陽圧吸入法」や「J045 人工呼吸」等との同一日における併算定は不可とされており、算定要件を満たさない場合における請求は認められません。
とくに急性期を担う病院では酸素投与を複数の処置として行う場合があるため、酸素吸入の併算定ができるか否かについては確認を必ず行う必要があります。
酸素吸入の算定要件とは?知っておきたいチェックポイント

酸素吸入を算定するには、ただ酸素投与を行えば良いというわけではなく、算定要件を満たす必要があります。算定要件を正しく理解していなければ、せっかくの処置も算定できずに査定や返戻のリスクが高まります。ここでは、算定が認められるために押さえておきたい重要な条件やポイントを解説します。
医学的に必要な患者の状態であること
酸素吸入の算定には、患者の呼吸状態などが医学的に必要と認められることは前提条件です。
診療報酬は医学的な必要性に基づいて算定が認められるため、患者の酸素飽和度や呼吸困難の有無が重要な判断材料となります。
例えば、血液ガス分析やパルスオキシメーターの数値で基準値を下回っている場合や、呼吸状態の悪化が明確な場合に酸素吸入を行います。
いずれも診療録として医師の所見など充実した記録が求められます。
適用となる疾患名を確認する
レセプト作成時は、必ず適用疾患名の記載があるかを確認しましょう。
酸素吸入は特定の診療科や疾患に限られず、内科系・外科系、入院・外来問わず実施される診療行為です。
しかし、すべての患者が対象となるわけではなく、急性期疾患や慢性呼吸不全など、保険診療上で認められた適用範囲が定められています。
例えば、呼吸器科や循環器科での使用が多いほか、在宅医療でも条件を満たせば算定できますが、適用外の疾患での算定は認められません。
DPC対象病院の場合はレセプトに記載できる疾患名の数に上限があるので、診療内容を加味しながら疾患名の選択をしていきましょう。
併施、併算定の診療行為における算定要件の確認
診療報酬のルール上、前述のとおり一部の診療行為では「酸素吸入」との併算定が認められていないものや、「酸素吸入」の手技料が包括されるものがあります。
下記のいずれかとの酸素吸入の併算定はできません。該当する行為がないか、酸素投与を実施していた場合は必ずチェックをしましょう。
酸素吸入が含まれる診療行為の例
特定入院料(使用した酸素及び窒素の費用は別途算定可。)
- A300 救命救急入院料
- A301 特定集中治療室管理料
- A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料
- A301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
- A301-4 小児特定集中治療室管理料
- A302 新生児特定集中治療室管理料
- A302-2 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料
- A303 総合周産期特定集中治療室管理料(母体・胎児集中治療室管理料、新生児集中治療室管理料)
- A303-2 新生児治療回復室入院医療管理料
- A305 一類感染症患者入院医療管理料
在宅患者診療・指導料
下記いずれかを算定した月の酸素吸入の費用は算定不可
- C000 往診料 注3 酸素療法加算
下記いずれかを算定している患者に対して行った酸素吸入の費用は算定不可(これに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)
- C103 在宅酸素療法指導管理料
- C107 在宅人工呼吸指導管理料
- C107-3 在宅ハイフローセラピー指導管理料
処置
下記いずれかと同一日に行った酸素吸入の費用は算定不可
- J026 間歇的陽圧吸入法
- J026-2 鼻マスク式補助換気法
- J026-3 体外式陰圧人工呼吸器治療
- J028 インキュベーター
- J026-4 ハイフローセラピー
- J045 人工呼吸(補助呼吸装置による持続陽圧呼吸法(CPAP)及び間歇的強制呼吸(IMV)を含む)
- J045-2 一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施する場合、その他の場合)
- J050 気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)
麻酔
下記麻酔を算定した場合における酸素吸入の費用は算定不可
- L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔
リハビリテーション科
下記リハビリテーションに付随する諸検査及び呼吸機能訓練と同時に行った酸素吸入の費用は算定不可
- H003 呼吸器リハビリテーション料
酸素吸入の算定で押さえるべきレセプトの記載方法と注意点

酸素吸入の算定を審査で認められるには、レセプトやカルテの記載方法を正しく理解し、実践することが不可欠です。なお、記載が不十分だと査定や返戻をされやすくなるため、具体的な記載のポイントを知っておくことで、不要な査定や返戻を未然に防げます。ここでは、実務で役立つ記載方法と注意点をご紹介します。
レセプトには具体的な疾患名を記載する
レセプトには酸素吸入の実施理由や患者の状態が分かるよう、具体的な疾患名を記載することが重要です。これは、審査側が処置の必要性を判断できるよう、客観的かつ詳細な情報を示す必要があるためです。
審査側にはカルテの情報がないため、レセプトにある疾患名や診療行為を中心に審査が行われます。したがって、単なる「低酸素血症」の記載だけでは酸素投与の必要性が不明瞭と判断されかねません。対策の例として「重症肺炎」や「急性呼吸不全」といった酸素投与を要する疾患名の記載がポイントとなります。
また、「重症肺炎に伴う呼吸不全を認めたため、●●リットル/日の酸素吸入を実施した」、「入院後に呼吸状態が悪化し、酸素飽和度が●%を下回ったため酸素投与を行った」といった診療経過を症状詳記として記載することで、査定のリスクを減らせます。
また、必要に応じて検査値の時系列と酸素投与量等、数値データを客観的な根拠資料として請求時に添付することも有効です。
看護記録や処置記録に酸素吸入の開始時間や患者の状態変化を残す
カルテや看護記録等には酸素吸入の開始・終了時間や患者の呼吸状態の変化を詳細に記録するよう、診療部や看護部と協力して対応しましょう。
適切な算定をする上では、1日ごとに投与量を計算しなければなりません。
したがって、酸素を投与した開始・終了時間や投与量の記録が必要であり、記録に基づき算定を行います。
レセプト上、酸素吸入の手技料は1日ごとに算定するため、投与時間の記載等は不要ですが、酸素の投与量も患者の状態・重症度を示す1つの情報になり得ます。そのため、適正・適切な請求・審査のためにも、実際の診療に基づいて請求を行います。
適時調査では、診療録に記録がなければ算定の根拠が不十分と判断されるため、返還金の対象となり得ます。返還となった事例では「酸素投与に係る具体的な記録がなかった」ことを理由に指摘されたケースが多く報告されています。
また、査定審査後に再審査請求をする場合、記録に基づき症状詳記を作成するため、適切な記録は診療にあたる医療従事者全員が行う必要があります。
算定要件における「注」記載を確認する
「酸素吸入」の告示では下記のとおり「注」の記載があります。
注1 使用した精製水の費用は、所定点数に含まれるものとする。
したがって、酸素投与時に使用した精製水は算定ができません。
カルテに使用した記録があったとしても算定不可であるため、レセコンにオーダーとして入力があった場合は精製水の削除または院内データのみとして請求はしないようにしましょう。
ちなみに、臨床現場の方のお話では、気道の乾燥を防ぐ目的で精製水を使うそうです。
投与する酸素には湿度がないらしく、乾燥した酸素を投与し続けると気道の粘膜が刺激されて充血したり、繊毛運動の低下を引き起こし、結果として肺炎や無気肺などにつながってしまうのだそうです。
FAQ
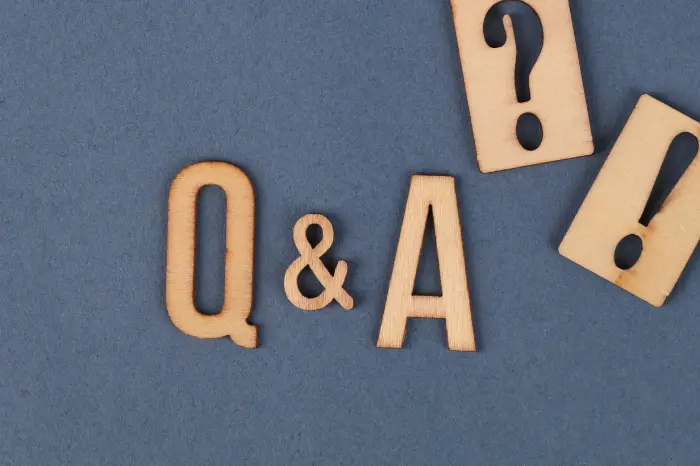
以下、よくあるQ&Aを記載しています。
まとめ:酸素吸入の査定・返戻を防ぐために今すぐできる対策

酸素吸入の算定で返戻や査定を防ぐためには、診療報酬制度の理解だけでなく、日々の業務に役立つ具体的な対策が必要です。ここでは、すぐに実践できるポイントをまとめてご紹介します。正しい対応でスムーズな請求を目指しましょう。
診療報酬制度の理解を深め、算定要件を正確に把握する
まずは「酸素吸入」の診療報酬における算定要件を正確に理解することが重要です。
診療報酬制度の基礎を知らなければ、誤った請求や査定のリスクを避けられません。
最新の診療報酬点数表や厚労省の通知、指導事例等を定期的に確認することで、適切な対応が可能になります。
院内で算定基準や記録ルールを共有し、統一化する
院内で酸素吸入の算定基準や記録方法をルール化し、職員全員で共有しましょう。
ルールの統一がなければ、担当者ごとの認識のズレでミスや確認不足が起こりやすくなります。自分が知らなかったことを別の担当者に聞いたら、実はその担当者も知らなかった、ということはよくあります。職員全員で知識や認識の共有を行っていくいことで業務水準が高くなっていきます。
院内研修やマニュアル作成、チェックリストの導入なども実務の標準化が進み、査定などの防止に効果的です。
不明点は積極的に上司や担当医に確認する
酸素吸入の算定は診療報酬のルールに基づいて算定しなければなりません。また、医学的必要性や記録がなければ査定や返戻、返還金の対象になり得ます。
そのため、疑問や不明に思う点があれば早めに上司や担当医に相談することが大切です。必要に応じて審査支払機関に確認することもよいでしょう。
理由は自己判断による誤請求を避け、適切な対応策を迅速に見つけられるからです。また、自分が気になって調べたことは忘れにくいため、同じ誤りを防ぐことにもつながります。
請求を誤ると、患者さんへの請求額も変わり、差額の調整をすることも窓口での業務負荷を増やすことになります。また、レセプト請求でも査定や返戻になると、再審査請求の検討や再請求の手間も増えてしまいます。
診療報酬制度の理解と院内ルールの統一、疑問点の相談を徹底し、算定のミスを防いでスムーズ、かつ適切な請求を目指していきましょう。
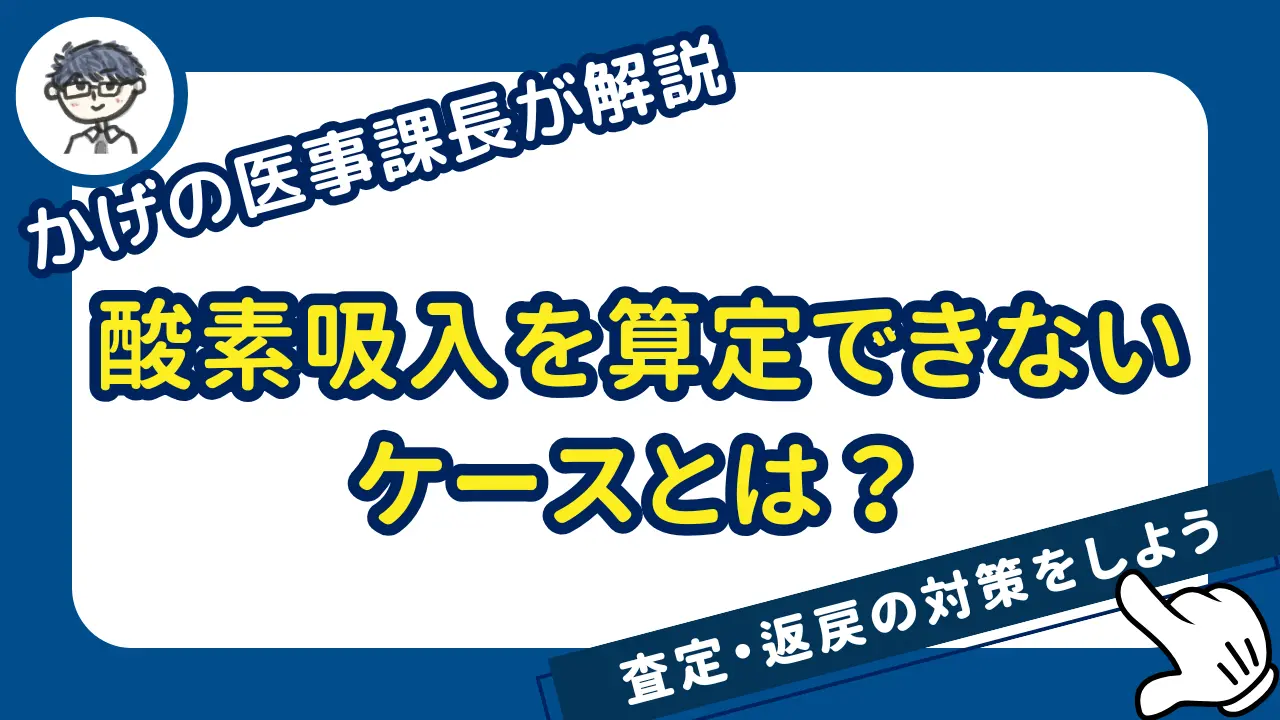
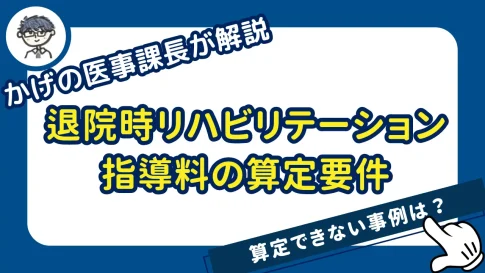
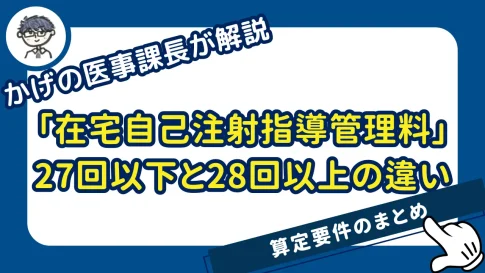
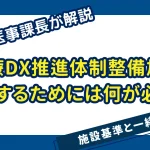

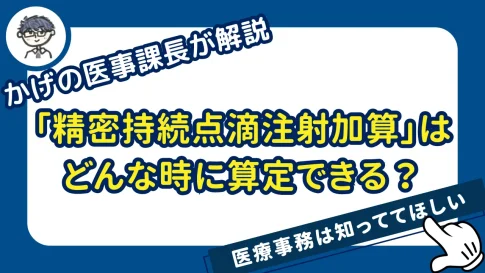
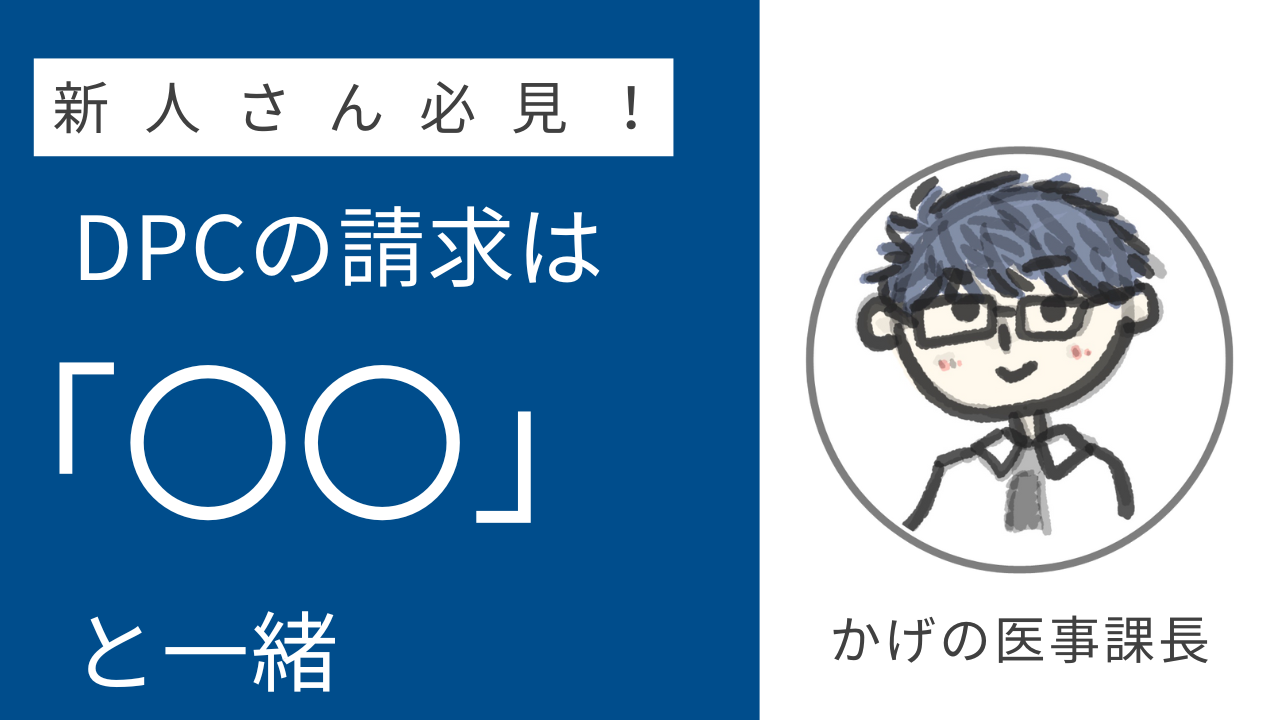
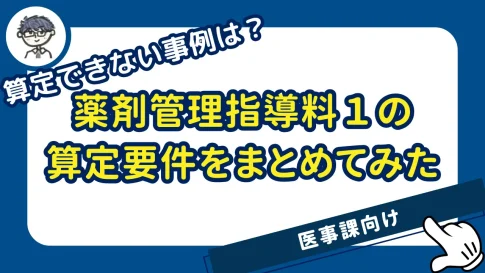
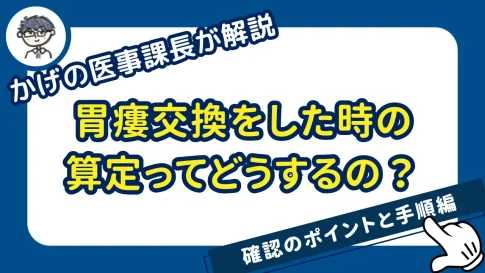
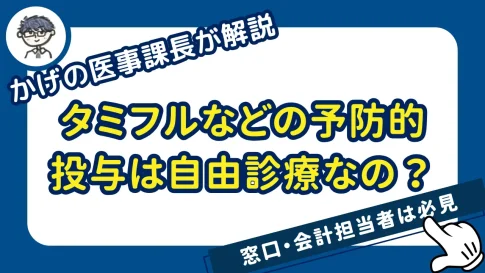
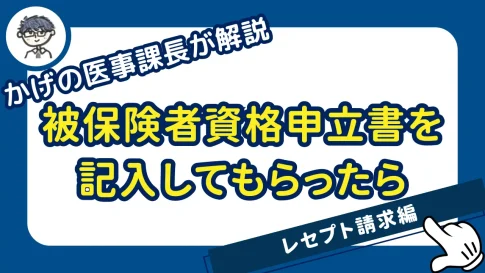
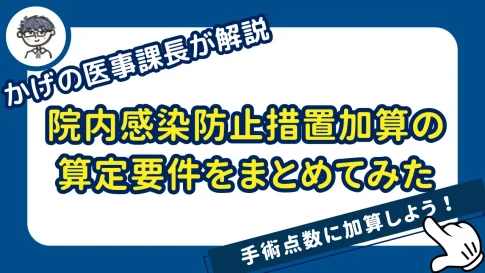
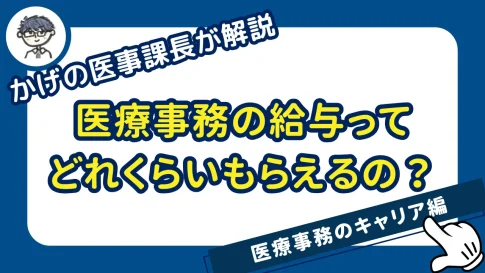
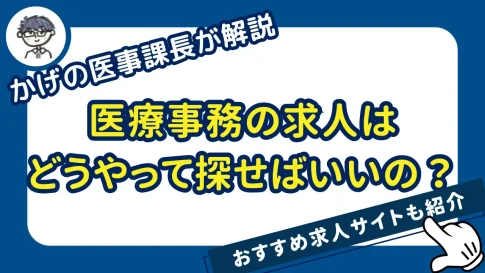
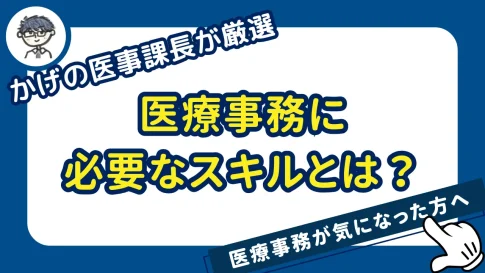
患者さんに対して酸素を投与した場合(酸素療法)において、1日当たりの診療報酬として算定する診療行為のこと。入院・外来(在宅含む)、また、病院・診療所問わず実施される診療行為である。診療報酬上は「処置」に分類され、レセプトの診療区分は「40」にて記載する。酸素吸入の算定時は、通常、処置に使用した材料として酸素を併せて算定する。