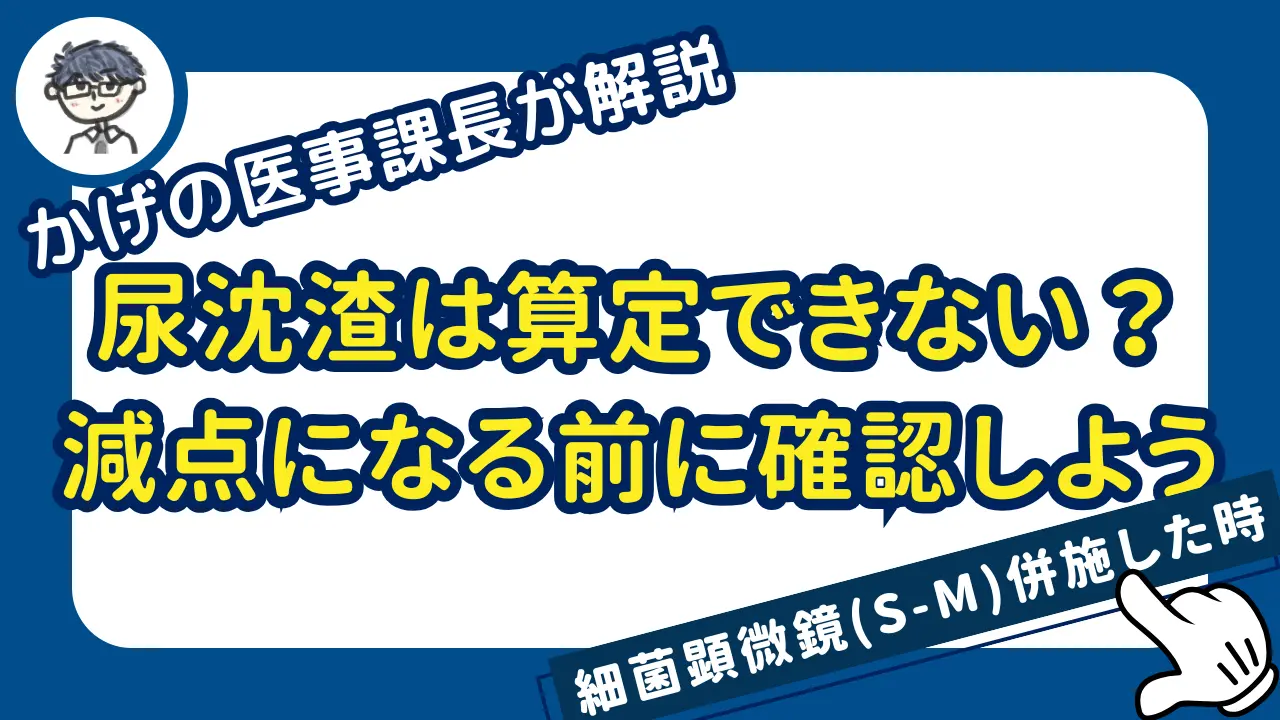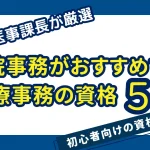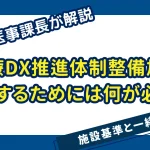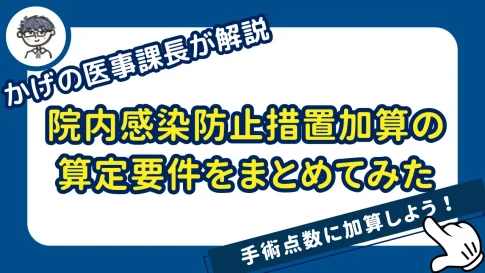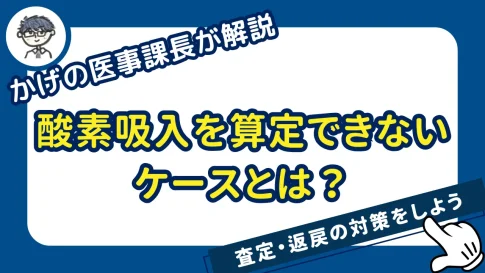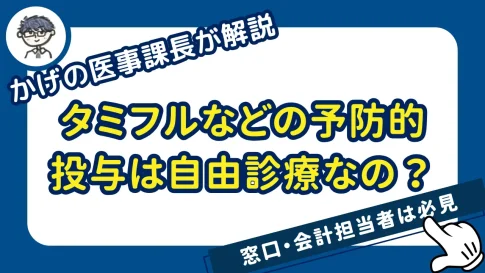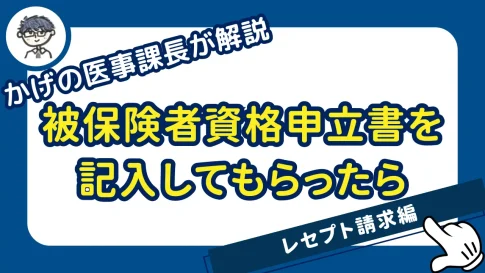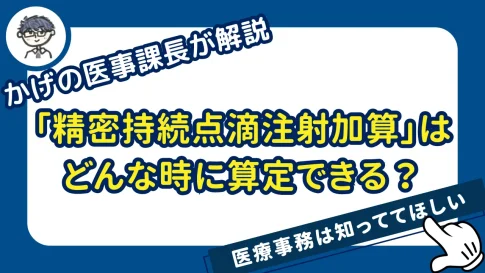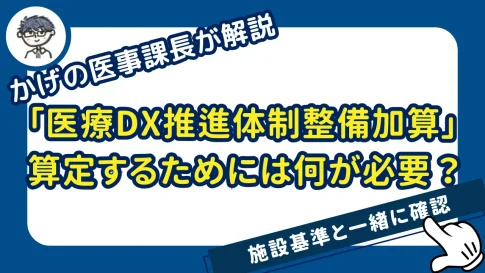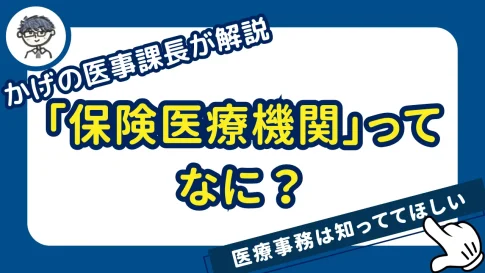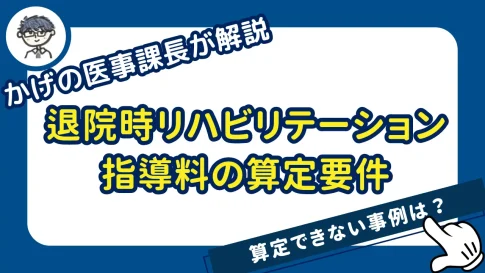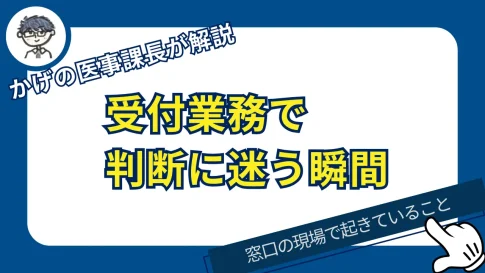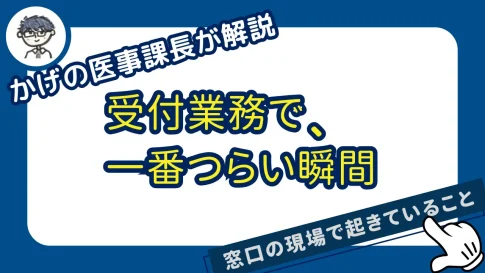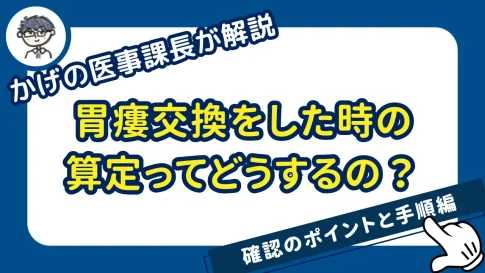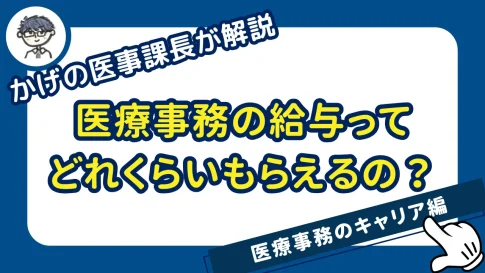病院、クリニックに関係なく実施することが多い「尿沈渣」の検査ですが、算定できないケースがあることをご存知でしょうか。
レセプト請求をする前に病名チェックをしたのに、審査の結果は減点されてしまった!という経験がある方は、私だけではないと思います。
適切な算定、病名チェックができることは医療事務の重要なスキルの1つです。
本記事では「尿沈渣」の算定ルールについて確認していきましょう。
※本記事は2024年度制度改定の内容です
- 尿沈渣検査を適切に算定できるようになり、不要な減点を避けられる
- 尿沈渣検査の適用病名が分かる
- 尿沈渣検査と細菌顕微鏡検査(S-M)を併施した際の算定のポイントが分かる

出来高で算定する場合はよく減点されやすいですよね。内科系・外科系はもちろん、入院・外来どちらにおいても実施する症例が多いと思うので、減点されないように本記事で一緒に確認していきましょう!
- 同一検体で尿沈渣検査と細菌顕微鏡検査(S-M)を併施した場合、「尿沈渣」の算定はできない
- ただし、判断料を考慮し、点数比較をしてから判断する
目次
「尿沈渣」とは?

診療報酬では「尿・糞便等検査」の区分に該当し、区分番号は「D002」と「D002-2」の2種類あります。
同じ「尿沈渣」でも、検査の方法によって異なる点数が設定されています。
- D002 尿沈渣(鏡検法) 27点
- D002-2 尿沈渣(フローサイトメリー法) 24点
どんな検査なの?
「尿沈渣」は尿を検体として調べる検査の1つです。
尿を遠心分離器にかけ、赤血球、白血球、上皮細胞、細菌等を調べる検査とされ、腎・尿路系疾患の診断や治療効果の判定などに用いられるようです。
「尿沈渣」の算定要件
詳細は医科点数表をご確認いただきたいのですが、概要を以下にまとめます。
- 同一検体で「尿沈渣」と「D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査(S-M)」を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する
- 尿沈渣(鏡検法)と尿沈渣(フローサイトメリー法)を併せて実施した場合、主たるもののみ算定する
- 「D000 尿中一般物質定性半定量検査」もしくは「D001 尿中特殊物質定性定量検査」において何らかの所見が認められ、または診察の結果からその実施が必要と認められて実施した場合に算定する
- 原則として、自院内で検査を行った場合に算定する
- 染色標本による検査を行った場合は、染色標本加算として、9点を所定点数に加算する(鏡検法のみ)
- 初診時の一般検査としての算定は、原則として認められない(支払審査基金の場合)
後述しますが、算定要件でポイントになるのは同一検体で「D017 の細菌顕微鏡検査(S-M)」併施した場合です。
レセプト請求後に減点される場合の多くは、この算定要件に引っかかってしまいます。
「尿沈渣」の適用病名

前述のとおり、腎・尿路系疾患が適用とされています。
糸球体腎炎、尿路感染症(膀胱炎や腎盂腎炎など)、尿路結石などを疑って実施されることが多いようです。
レセプトの病名をチェックする時には腎・尿路系疾患があるかを確認しましょう。
もし、病名がない場合は担当医に確認が必要です。
本記事執筆時における支払基金の審査事例をもとに、適用が認められるものと認められないものを下記にまとめておきます(明示されたもののみ)。
「(疑い含む。)」と一部の病名には記載がありますが、経験上では確定診断が必須ではない印象です。
疑い診断でも審査では認められますが、短期間で複数回実施している場合は、保険診療に馴染まない(療養担当規則に則っていない)と判断される場合があります。
D002 尿沈渣(鏡検法)を算定した時
認められる病名
- 糖尿病性腎症
- 溶連菌感染症
認められない病名
- 高脂血症
- 脳血管障害
- 腎臓疾患・尿路系疾患以外(再診時)
D002尿沈渣(鏡検法)の染色標本加算を算定した時
認められる病名
- 尿路感染症(疑い含む。)
- 腎炎(疑い含む。)
- 腎盂腎炎
- 腎(機能)障害(疑い含む。)
- 腎不全(疑い含む。)
- 慢性腎臓病
- 特発性腎出血
- 前立腺炎
認められない病名
- 急性上気道炎
- 高血圧症
- 腹痛
D002 尿沈渣(フローサイトメリー法)を算定した時
認められる病名
- 糖尿病性腎症
- 溶連菌感染症
認められない病名
- 高脂血症
- 脳血管障害
- 腎臓疾患・尿路系疾患以外(再診時)
審査で減点されないために

保険診療を前提とした診療報酬の請求では、病名の適用はもちろん、算定要件を満たさないままレセプト請求をすることは減点につながります。
減点されないために見落としがちな算定要件を確認しておきましょう。
細菌顕微鏡検査と併せて実施した場合はカルテで検体を確認する
算定要件で触れたとおり、細菌顕微鏡検査(S-M)を併施した場合にそのまま請求してしまうパターンは、どの医療機関でも多いのではないでしょうか。
実施した検査は基本的に請求できるだろう、と思いがちですが、頻回に実施することが多い検査ほど算定要件は気を付けなければなりません。
ここで、改めてポイントとなる算定要件を下記に示します。
同一検体で「尿沈渣」と「D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査」を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する
ここでポイントなのは、「同一検体で」というところです。
「D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査(S-M)」は、尿、糞便、喀痰、穿刺液、胃液、十二指腸液、胆汁、膿、眼分泌液、鼻腔液、咽喉液、口腔液、その他の滲出物等を検体として行う検査であり、「尿沈渣」同様に尿を検体として実施する場合があります。
したがって、「尿沈渣」と「細菌顕微鏡検査(S-M)」を実施した場合は同一検体で実施する可能性が高いので、同一検体での実施有無について、カルテや検査部の方に確認をしましょう。
同じ尿を検体として併施していた場合、「尿沈渣」の算定はできない
算定要件にあるように、同じ尿を検体として「尿沈渣」と「細菌顕微鏡検査(S-M)」を実施していた場合は、「尿沈渣」の算定はできません(0点)。
したがって、「細菌顕微鏡検査(S-M)」のみを算定することになります。
なぜ「尿沈渣」の算定ができないのか?というと、算定要件に「主たるもののみ算定する」と記載されているからです。
「細菌顕微鏡検査」は検査方法によって3種類の点数設定がされています。
1 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの 50点
2 保温装置使用アメーバ検査 45点
3 その他のもの 67点
多くの医療機関では「3 その他のもの 67点」を算定することが多いかと思いますが、1~3のいずれと比べても細菌顕微鏡検査(S-M)の方が点数が高いことが分かります。
「主たるもののみ算定する」は「点数が高いものだけ算定する」と解釈できるため、同一検体で「尿沈渣」と「細菌顕微鏡検査(S-M)」を併施した場合は、「細菌顕微鏡検査(S-M)」のみを算定するということになります。
なお、算定要件上は「尿沈渣」と「細菌顕微鏡検査(S-M)」を同時に算定する場合は、コメントコードを用いて細菌顕微鏡検査に用いた検体の種類を記載することとなっています。
尿検体であれば「尿沈渣」の算定要件を満たさないので「尿沈渣」が減点対象となりますし、「尿以外の検体」であれば「尿沈渣」と「細菌顕微鏡検査(S-M)」のどちらも算定要件は満たすことになります。
検体の情報がないと適切な審査ができなくなってしまうため、不要な減点や返戻を避けるためにも、併算定時のコメントコードの記載は忘れずに行いましょう。
また、診療上でどうしても必要になって実施した検査を算定する場合は、医師の所見や検査の必要性等を記載した上でレセプト請求することが望ましいですが、確実に審査で認められるとは限らない点は留意が必要です。
「細菌顕微鏡検査(S-M)」の算定をしないケースもある
尿の同一検体で「尿沈渣」と「細菌顕微鏡検査(S-M)」を実施していた場合は、「尿沈渣」の算定はできない(細菌顕微鏡検査(S-M)を算定する)、とお伝えしたばかりですが、逆に「細菌顕微鏡検査(S-M)」を算定しないケースもあります(稀のような気もしますが)。
具体的には同月内に複数回受診し、それぞれで「細菌顕微鏡検査(S-M)」を算定しないケースを実施した場合です。
なぜ「細菌顕微鏡検査(S-M)」を算定しないケースもあるのか?というと、検査料+判断料で点数を比較する必要があるからです。
「尿沈渣」の場合、検査の判断料としては「尿・糞便等検査判断料 34点」が算定できます。
「細菌顕微鏡検査(S-M)」の場合は、「微生物学的検査判断料 150点」が算定できます。
これを加味した上で考えると、「細菌顕微鏡検査(S-M)」を算定しない方がよいケースは、下記に該当する場合です。
- ある月の1回目の受診:「尿沈渣」と「細菌顕微鏡検査(S-M)」を併施し、「尿沈渣」以外に「尿・糞便等検査判断料 34点」を算定できる検査を実施していない
- 同月内2回目以降の受診:「尿沈渣」と「細菌顕微鏡検査(S-M)」を併施し、その月に「尿・糞便等検査判断料 34点」を算定していない
実際に検証してみましょう。
【1回目の受診】
1.「尿沈渣(染色標本加算あり) + 尿・糞便等検査判断料」 = 70点
2.「細菌顕微鏡検査(S-M)その他 + 微生物学的検査判断料」 = 217点
2.の方が点数が高いため、217点のみの算定となります。この時、尿沈渣は算定できないため、尿・糞便等検査判断料の算定もできないことになります。
【2回目以降の受診】
1.「尿沈渣(染色標本加算あり) + 尿・糞便等検査判断料」 = 70点
2.「細菌顕微鏡検査(S-M)その他」 = 67点
この場合は、1.の方が点数が高くなるため、「細菌顕微鏡検査(S-M)」を算定しない方がレセプト請求上はよい、ということになるのです。
もちろん、他検査で判断料を既に算定している場合は該当しないため、「細菌顕微鏡検査(S-M)」のみを算定した方がよいケースに該当します。
まとめ
前述のとおり、同一検体で「尿沈渣」と「尿沈渣」と「細菌顕微鏡検査(S-M)」を併施した場合は、「尿沈渣」の算定はできないことになります。
したがって、「尿沈渣」と「細菌顕微鏡検査(S-M)」をしていたら、まずは同一検体で検査を行ったかどうかを確認しましょう。
同一検体の場合は(その月の判断料の算定も考慮した上で)「細菌顕微鏡検査(S-M)」のみを算定し、別検体の場合は「細菌顕微鏡検査(S-M)」の検体について、レセプトのコメントコードを用いて記載します。
どの医療機関でも頻回に行われる検査なので、減点されないように適正・適切な算定方法を身につけていきましょう!